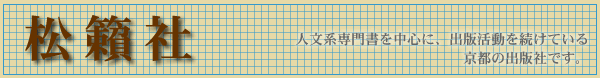|
| 蔵書一代 |
| なぜ蔵書は増え、そして散逸するのか |
| 紀田順一郎 著 |
| 2017年7月発行 |
| 定価:1800円+税 |
| ISBN:978-4-87984-357-9 |
| 販売完了いたしました |
内容紹介
「すると、蔵書一代、ですね」
「うん? 蔵書一代? そうだ、本当にその通りだ。愛書家の息子に愛書家なしだ」
「書肆・蔵書一代、というのが当店の名です。よろしく」
「ほう。あんたは面白い人だ」
「面白いといえば、こんな詩がありますよ。
蔵書一代
人また一代
かくてみな共に死すべし」
「はっはっは、これはいい」と、老人は初めてうちとけたようだった。「これはいい、共に死すべしか、はっはっは」
(紀田順一郎著『古本屋探偵の事件簿』より)
「わが亡きあとは売りてよね(米)買え」と蔵書印に彫った江戸時代の蔵書家は、蔵書の一代性を知っていた。彼らには自分の個性が分割されえぬ一回性のものだという誇りがあり、それを体現した蔵書が自分の死とともに破壊されるべきことが確認されていた……
しかし、蔵書一代は感傷ではなく、一つの諦観、悟りである。つまり、所蔵者の死後、一冊一冊の書物が別の蔵書体系の中に再生するのを拒むものではないのだ。むしろそれこそは、蔵書といういじましい行為における唯一の救いなのではあるまいか。
(紀田順一郎著『読書の整理学』より)
やむをえない事情から3万冊超の蔵書を手放した著者。
自らの半身をもぎとられたような痛恨の蔵書処分を契機に、「蔵書とは何か」という問題に改めて取り組んだ。
近代日本の出版史・読書文化を振り返りながら、「蔵書」の意義と可能性、その限界を探る。
【目次】
序 章 〈永訣の朝〉
第Ⅰ章 文化的変容と個人蔵書の受難
第Ⅱ章 日本人の蔵書志向
第Ⅲ章 蔵書を守った人々
第Ⅳ章 蔵書維持の困難性
参考文献
あとがき
著者年譜
著者紹介
紀田順一郎(きだ・じゅんいちろう)
評論家・作家。1935年横浜市に生まれる。慶應義塾大学経済学部卒業。
書誌学、メディア論を専門とし、評論活動を行うほか、創作も手がける。
主な著書に『紀田順一郎著作集』全八巻(三一書房)、『日記の虚実』(筑摩書房)、『東京の下層社会』(同)、『生涯を賭けた一冊』(新潮社)、『知の職人たち』(同)、『古本屋探偵の事件簿』(創元推理文庫)、『日本語大博物館』シリーズ(ジャストシステム)、『昭和シネマ館』(小学館)、『横浜少年物語』(文藝春秋)、『幻島はるかなり』(松籟社)など。『幻想と怪奇の時代』(松籟社)により、2008年度日本推理作家協会賞および神奈川文化賞(文学)を受賞。
訳書に『M・R・ジェイムズ怪談全集』(東京創元社)など。荒俣宏とともに雑誌「幻想と怪奇」(三崎書房/歳月社)を創刊したほか、叢書「世界幻想文学大系」(国書刊行会)を編纂。
ご購入方法
本書は全在庫の出荷を完了いたしました。誠にありがとうございました。