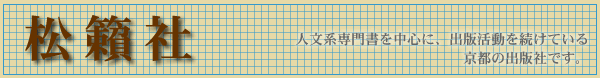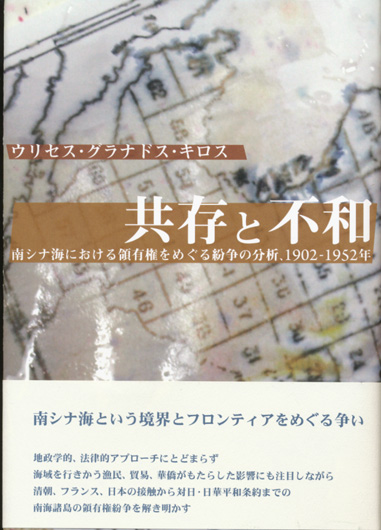 |
| 共存と不和 |
| 南シナ海における領有権をめぐる紛争の分析、1902-1952年 |
| ウリセス・グラドナス・キロス 著 |
| 2010年2月28日 |
| 定価:5,500円+税 |
| A5判・ハードカバー・304ページ |
| ISBN:978-4-87984-275-6 |
| 在庫あります |
内容紹介
地政学的、法律的アプローチにとどまらず、中央と地方(植民地)の対立や、海域を行きかう領民、貿易、華僑がもたらした影響にも注目しながら、清朝、フランス、日本の接触から対日・日華平和条約までの、南シナ海という境界とフロンティアをめぐる争いを解き明かします。
この本の目次
前書き
第1章 歴史的背景
第1節 明清代における南シナ海
「西洋・東洋」と南シナ海
海域の知識と支配
新たな分析の必要性
第2節 1902-1939年における南シナ海をめぐる中国とフランス・ベトナム間の領有権問
中国・ベトナム間の領有権問題をめぐる重要性
中国への対抗――ベトナムの立場
「海洋の境界」を守る課題――中国の立場
中国とフランスの争点
中国およびフランスの主張の特質――海洋政策と海域概念
島嶼の領有権をめぐる「時期的な変遷のパターン」について
第3節 大日本帝国による南シナ海の地政上の関心とその開発――1902-1939年
日本の拡張政策の原理
1921-1922年のワシントン会議前後の太平洋における日本の海洋利益
南シナ海における先進の前期段階――植民地的な開発
紛争への道――軍国主義と経済拡大
南シナ海における先進の後期段階――海軍占領や日仏紛争、1937-1939年
南シナ海と大日本帝国――歴史的観点からの評価
第4節 1939年までのアメリカ、イギリスによる南シナ海への関与
「大英帝国」と南シナ海
イギリスによる南シナ海の島嶼への関与
南シナ海の周辺とアメリカ――フィリピンとの関係
日仏の間の「新南群島」問題とアメリカ
第2章 過渡期における南シナ海――1946-1952年
第1節 第二次世界大戦直後の中国側による領有権の主張
中国の主張と戦後の新時代
政府による領有権の主張、1946-1949年
過渡期の混乱、1949-1952年
現代の海洋政策の構成――主張と経済的開発
南シナ海をめぐる戦後の海洋政策の構成と島嶼の領有権の主張
第2節 第二次世界大戦直後の英仏による南シナ海への関心
フランスの南シナ海への復帰
南北ベトナムの成立とフランスによる領有権の主張
東南アジアにおける優先事項を整理したイギリス
南シナ海における植民地化の晩期
第3節 フィリピンの独立とスプラトリー群島に対するフィリピンの主張
南シナ海における新たな当事者
クロマによるフリーダム・ランドの発見と南沙群島におけるその後の出来事
南シナ海の島嶼をめぐるフィリピン政府の立場
現在から見たフィリピンの歴史叙述
第4節 1951年の対日平和条約と南シナ海における地域海洋秩序形成の失敗
サンフランシスコ会議への道
中華人民共和国と中華民国の欠席
条約における西沙群島・新南群島の帰属について
戦後の太平洋における南シナ海の地政的な意味――概念化
第3章 1902-1952年における社会・経済的な共存の海域としての南シナ海
第1節 人間の移動の海域
社会・経済上の海域としての南シナ海
南シナ海における主な人間の移動――東南アジアへの華人の移民
南シナ海における日本人の移民――航海自由と植民地化
人間の移動と南シナ海の支配――領有権の主張と国民の移動との関係
第2節 南シナ海における航海、交易ネットワークおよび漁業
経済上の複合的な関係の海域
南シナ海における航海ルートおよび地域貿易
漁業開発としての海域
経済上の活動と領有権の主張――南シナ海における社会・経済・政治上の関係
第3節 国境を越える南シナ海――「中心-周辺」および「中央?地方」の緊張
隣接諸地域における中心と周辺
南シナ海の統治、共存をめぐる「中央?地方」の問題について
結論
註
後書き
参考文献
ご購入方法
本書は、大型書店を中心に、全国の書店でお求めになれます。
お近くの書店にないとき、お急ぎでご購入されたい場合は、小社へ直接お申し込みください。お電話でしたら075-531-2878まで。サイト上からのご注文は、左フレームの「お問い合わせ」→「書籍のご注文」からどうぞ。サイトから(あるいは電子メールで)ご注文いただいた場合は、送料無料です。書籍をお送りする際に、手数料無料の郵便振替用紙を同封いたします。
以下のサイトでもご購入できます。
→Amazon.co.jp
→hontoネットストア
→セブンネットショッピング
→ブックサービス
関連書
社会・教育