2016/2/15
書店での本との出会い 2:アレハンドロ・サンブラ『家への帰り方』
ニューヨークのストランド書店で、頭をそらして見上げたり、屈みこんで頭を傾げたりしながら巨大な本棚を眺めていると、アレハンドロ・サンブラの英語訳がいくつか並んでいた。いちばん新しいものは昨年(2015)4月に出た短篇集『マイドキュメント』(スペイン語版は2014年1月)。その裏表紙には「ボラーニョ以降、チリ出身の最も話題の作家」という『ニューヨーク・タイムズ』の評が載っている。短篇集がこれほど早く英訳されるのも珍しいことだが、やはり「最も話題」であるためか。
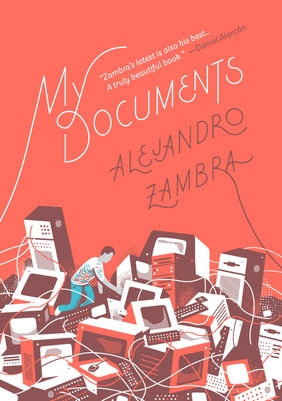
『マイドキュメント』英訳版
My documents
(Mcsweeneys Books, 2015)
帰国してサンブラの本を探すことにする。ところが、研究室にあった本は引っ越すときに箱詰めしたまま部屋や廊下に2、3列になって山積みされたままであり、そこから掘り出すのも難儀。せめて本棚くらいは調べようと思うが、そこも前後2列にめいっぱい詰まっており、奥に何があるのかわからない。やっとのことで見つかったのは中篇『家への帰り方』(2011)だけ。サンブラの処女作は2006年に出したBonsái。いまさら山積みの箱を開けるよりはもう一冊買った方が簡単と思い、AMAZONで検索するが「在庫切れ」。どうするか考えているとき、ふと娘が行き当たりばったりのメキシコ旅行をしているのを思い出し、メールを送る。帰国間近で、メキシコ・シティに戻ったら、最後の日にポランコにあるデパート、リベルプールに行くという。それではということで、メキシコに行くときに必ず出かける書店のサイトを検索する。あいにくGandhi(ガンディ)はNO DISPONIBLE(在庫なし)。続けてSótano(ソタノ)を見ると在庫がある。そしてリベルプールから2.5kmほど離れたソクラテス通りに支店がある。ただその支店の在庫は確認できず、店に行ってもないかもしれない。とりあえず、その旨を綴って、メールする。すると無事、入手の朗報。
こうしてようやくのことでBonsáiを再読。わずか95ページのこの中篇は次のような書き出しで始まる。
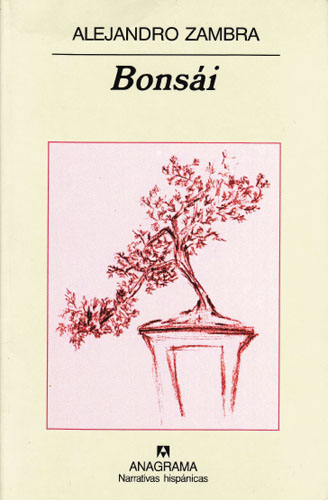
Bonsái原書
(Anagrama, 2006)
最後に彼女は死に、彼はひとりになる。ほんとは彼女、エミリアが死ぬ何年も前からひとりだったのだが。彼女の名はエミリアという、あるいはエミリアといった、そして彼の名はフリオという、あるいはフリオといった、そしてフリオであり続けている、ということにしておこう。フリオとエミリア。最後にエミリアは死に、フリオは死なない。あとは文学。
この冒頭の部分がとてもいい。こんな書き方をした本に出会ったことはなかったが、読み終われば、なぜサンブラが話題にのぼる作家なのかがよくわかる。作家志望の学生(若者)フリオとエミリアの恋物語と言ってしまうと身も蓋もないが、コミュニュケーションがうまくとれない孤独な若者たちが人の温もりを求めてする、現代的な恋愛のありようが淡々とした口調で語られ、これまでのイスパノアメリカの小説にはないような味わいがある、というよりは、むしろ特筆すべきは、そんな味わいを出しているその描き方・構成の清新さだろう。おまけに古い人間には昔懐かしい「アンニュイ」な、物憂い雰囲気さえ味わわせてくれる。
そうしたことを含めて、この作品を紹介しなくてはと思い立つ。だが、そのためにはまず日本語でのタイトルを確定しなくてはならないが、Bonsáiという言葉に引っかかる。これは「盆栽」でいいのだろうか。なぜなら、例えば、「漫画、マンガ、MANGA」と綴りが変わると微妙な差異が浮かび上がるからで、いまや世界的に認知されている日本の盆栽についても同じことが言い得るような気がする。「盆栽」と「Bonsái」は同じものなのか。サンブラの作品名「Bonsái(スペイン語ではaの上にアクセント符号が付いている)」はどのように訳されているのか。同書の翻訳名をAMAZONで調べてみると、Bonsai(英語、オランダ語、ドイツ語、イタリア語、ブラジル語)、Bonsaï(フランス語)、Bonzai(トルコ語)、mponsai / μπονσάι(ギリシア語)等々、どうやら「ボンサイ」という音をそのまま使っているらしい。ところがそうやって調べているうち、アメリカのAMAZONに『盆栽/木々の私生活(EXLIBRIS)』というタイトルが挙がっているのを発見。それを見て愕然となった。邦訳(松本健二訳、白水社)が2013年に出ていることを知らなかったからだ。そこで、もうタイトルのことで悩むのはやめた。

松本健二訳『盆栽/木々の私生活』
(白水社、2013)
白水社さんによる紹介ページはこちら
ネットにはこの『盆栽/木々の私生活』という本についての紹介やら書評やら読後感がたくさん載っているのでここで書く必要もないかもしれないが、折角なので少し。
エミリアがマドリッドに行ってしまったあと、フリオにはマリアという恋人ができる。定職のないフリオは、ガスムリという作家に会い、彼の手書き原稿を清書(パソコンに入力)する仕事にありついたとマリアに言うが、報酬をふっかけていたため、後でガスムリに断られる。ガスムリとの仕事が始まる、その作品のタイトルは『盆栽』だとマリアに嘘をついたため、彼自身が『盆栽』という小説を書き続けざるを得なくなる。
その本を書くためにフリオは「おそらくはもっとも役に立たないが、愛好家にはもっとも適した入門書の一冊」にある盆栽bonsáiについての説明を読む。
盆栽とは、木を縮小サイズで芸術的に表現したものである。それは生きた木と器という二つの要素からなる。二つの要素には調和が求められ、木に適した鉢の選択は、それ自体でひとつの芸術様式である。植えるのはつる植物でも灌木でも樹木でもよいが、当然ながらすべて木とみなされる。器は通常、鉢か趣のある岩石である。盆栽が「盆栽の木」と呼ばれることは決してない。「盆栽」という語が生きた要素をすでに含んでいる。鉢をとってしまえば、その木はもはや盆栽ではない。
何かの本からの引用と見なしうるが、出典は書かれていない。従って、サンブラが盆栽について書かれた本を読んでまとめたもの、あるいは独自に考えたものとも考えられる。いずれにせよこの説明から「盆栽の世話をすることはものを書くことに似ている、とフリオは考える。ものを書くことは盆栽の世話をすることに似ている」と考え、盆栽の世話をし続けることになる。ということはものを書き続けることになる。
本を書くにあたって、フリオは「盆栽」をイメージし、それを絵にし、できあがったものを眺めて「断崖に映える木」と思う。その絵は本文中に挿入されており、初版本のカバーデザインにも使われている(本の扉には絵の作者はLeslie leppeとある)が、出版元であるアナグラマ社は、いつからかは不明だが、その表紙を飾る盆栽の絵を替えた(邦訳の表紙はこの新しいものを使っている)。2枚を見比べると、新しいほうは、木の成長に合わせたわけでもないだろうが木の幹が太くなっているし、また、フリオの剪定技術が進歩したのか、うまく剪定がなされているようにも見える。
ところで、盆栽という言葉を目にするとよく思い出すことがある。学生時代、神戸の街を歩いていたときのこと。とある園芸店に入ったのだが、そこにたくさんの盆栽が並べられていた。しばらくあれこれ眺めていると、年配の男性が寄ってきて、興味あるんか、と言う。ええ、まあ、などと生返事をしていると、盆栽するんなら、早いとこ、いますぐ始めんと……、それ、まだ木にもなってへんのがあるやろ、あんたが定年という年になっても、40年くらい先のことやろー、だったら、そいつな、あれみたいに立派にはならへんでえ、木によっちゃあ、そこそこのもんになるけどな、まあどっちにしても40年分の思いは詰まるからな、自分で楽しむにはええけど、と言われた(だいたいこんな感じだったと思うが、脚色してるかもしれない。関西の言葉遣いは難しい。神戸の中でも違うくらいだから)。よく隠居した老人が盆栽をいじっているシーンが映画やドラマに登場するが、このとき初めて、盆栽を愛でるには歳月が必要であることに気づかされた。若い頃は老人趣味ととらえて、盆栽には近づかないものだが、『盆栽』の主人公はまるで、この年配の男性の忠告を素直に実践しているようにも思える。
閑話休題。『盆栽』は、「最後にエミリアは死に、フリオは死なない」と冒頭で記されているように、マドリッドに去ったエミリアの死をフリオが人づてに聞くまでの出来事が淡々と綴られている、そんな静かな作品でもある。
この『盆栽』のち、サンブラは2作目の中篇『木々の私生活』(2007)を発表する。詳しくは邦訳をお読みいただきたいが、これも前作に似た構成になっている。つまり主人公の現在と過去が交差する。つまり、「いま、ここ」という座標を確定するために記憶を呼び起こす。主人公フリアンは、大学で文学を教えるかたわら、小説を書く。ベロニカという女性と結婚、その連れ子のダニエラの3人で暮らしているが、ベロニカの帰りが遅いときには、「木々の私生活」というお話をしてダニエラを寝かしつける。ベロニカと結婚する前にはチリ大学の哲学科で学ぶ学生のカルラと暮らすが、やがてカルラはフリアンにとっては得体の知れない女性と知り合い、彼のもとを去る。その頃、彼は本を書き始めるのだが、何年もかけて書いた300ページもの原稿を削りに削って47枚の小説にする。その本は「盆栽相手にひとり閉じこもって、それが真の芸術作品になるかもしれないと心を震わせつつその世話をしている男の話」。そして、「両親はフリオにするつもりで戸籍係の前でそう伝えたが、担当官はそれをフリアンと聞き違え、出生証明書にもフリアンと書き込み、両親もそれを正そうとはしなかった」とあれば、フリオでもフリアンでもいいが、フリアンは『盆栽』を書いていることに、そして『木々の私生活』はフリオの後日譚という位置づけになる。フリアン、カルラ、ベロニカ、ダニエラ等々、登場人物が増え、それぞれの経歴が語られはするが、あくまでもフリアンの話であり、『盆栽』と同じような筆致で物語は綴られていく。
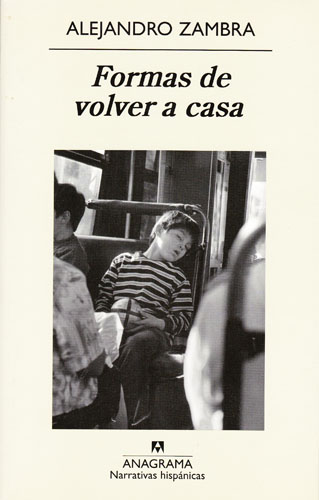
『家への帰り方』原書
Formas de volver a casa
(Anagrama, 2011)
『盆栽』、『木々の私生活』の2作に共通して言えることは、いずれも主人公は部屋、家といった限られた空間から出ないということ。ところが3作目の『家への帰り方』になると大きく変わる。主人公が外に出るからだ。それはタイトルからも明らかで、家を出なければ、家には戻れない。オデュッセウスはトロイアから帰宅するのに10年かかったが、わたしたちの大半が朝家を出て、夜家に帰るという暮らしを続けている。家を離れている間に、オデュッセウスのようなドラマチックな冒険をすることはほぼないのだろうが、それでも事件・事故に巻き込まれる可能性は皆無ではない。そう考えれば10年でも1日でも同じ。「小説のなかで誰かが家に帰らないとき、それはたいてい何か悪いことが起きたからだとフリアンは思う」(『木々の私生活』)。では『家への帰り方』の主人公はどんな体験をして家に帰るのだろうか。
この作品は「脇役」「親たちの文学」「子供たちの文学」「みんな元気」の4つに分かれている。「脇役」の舞台は首都の南西にある町マイプ。語り手である「ぼく」は6、7歳のとき、両親とはぐれるが、無事1人で家に帰りつく。父親は「いいことだ、おまえは逆境を乗り越えた」と言い、母親は、「おまえが道に迷わないことがわかったわ。一人で通りを歩けるって。でももっと道に気をつけててね。もっと早く歩いたほうがいいわ」と言う。以後、早足で歩く癖がつくが、クラウディアと初めて話したとき、そのわけを訊かれる。2人が知り合ったのは「一九八五年三月三日の地震のとき。でもそのときは話をしなかった。/クラウディアは十二歳、ぼくは九歳、だから親しくなることはありえなかった。でも友だち、友だちみたいなものだった。よく話し合った。その会話を思い出すためだけにこの本を書いてるのだとときどき思う」。こうして「ぼく」は子供という、社会の動きからすれば脇役に過ぎない時代、1980年代の体験を思い出していく。
「ぼく」は、クラウディアから、近所に住む伯父のラウルを見張って、その行動や様子を教えてほしいと頼まれる。クラウディアに会いたい一心でその役目を引き受け、ラウルの住む家を見張り、動向を監視し、その家から出てきた女性の跡を追い、バスに乗って遠くまで出かけたりする。そうして知ったことをクラウディアに伝えるのだが、ある日、彼女は待ち合わせの場所に、年長の男の子とやってきて、事情が変わったからもうラウルを見張らなくていい、と言う。落胆した「ぼく」は、その後、1年ほどクラウディアとは会わないが、ある日ラウルが車にいくつもの箱を積み込んでいるのを目撃し、クラウディアに知らせに行く。だが、彼女は数日前に出ていったと近所の人に言われる……。
あくまでも9歳の男の子の視線で描かれたこの「脇役たち」は、1980年代の独裁下にある大人たちの社会、年上の女の子に好意を寄せ、認めてもらいたいと思う少年の心の内、その少年を魅了するスパイという初めての冒険、そして女の子との予期せぬ突然の別れ、等々を巧みな構成で描き、これだけでも短篇とも言えるくらいの仕上がりになっている。
ところが、続く「親たちの文学」は次のように始まる。
少しずつ小説が進んでいる。まるでクラウディアがいるかのように、いたかのように、彼女のことを考えながら時を過ごす。最初、彼女の名前さえ疑っていた。だが、それはぼくの世代の九十パーセントの女性の名前だ。彼女がそういう名前であるのはあたりまえのことだ。その音の響きも嫌じゃない。クラウディア。/ 自分の登場人物たちに苗字がないことがとても気に入ってる。ほっとする。
こうして、ここで「ぼく」が小説を書いていることが、つまり、「脇役たち」は小説の一部であることが、明かされる。この「親たちの文学」での「ぼく」は作家で文学の教授であり、エメという女性と別れたものの、和解したがっている。しかし、別れて1年あまりたち、「ぼく」が貸した本の返却がきっかけで、彼女は「ぼく」の家にやってくる。そして、その後もたびたび彼女は「ぼく」のもとに姿を現すことになる。そのたびに「ぼく」は書きかけの原稿を読んでもらおうとするが、彼女はなかなか同意しない。そんな状態が続く一方、「ぼく」は自宅で、また、実家で小説を書き続けたり、『ボヴァリー夫人』を始め文学について考えたり、書いている小説について検討を加えたりする。
(略)きのう、ほぼ二十年後の再会のシーンを書いた。満足のいくできだったが、登場人物たちは再会してはならないのではとときどき思ったりする。何度もすれ違う、同じ街路を歩く、相手のことがわからずにカウンターの端と端とで話さなくちゃならないのではと。/二十年後に相手が誰か本当にわかるものだろうか?(略)出会わないほうが美しいように思える。現在にいたるまで、とても異なるそれぞれの人生をただ過ごし、その人生を少しずつ近づけていく。つまり、かち合うことのない平行する二つの軌道。でもそんな小説は他の誰かが書くべきじゃないか。それを読んでみたい。ぼくが書きたい小説では二人は出会うからだ。出会ってもらわないと困る。
この文に呼応するかのように、次の「子供たちの小説」では、「脇役たち」の後日譚が描かれる。33歳のクラウディアは父親の通夜が始まる直前にアメリカから帰国し、「ぼく」と再会する。クラウディアはアメリカでの話はせず、20年不在にしていたチリとのつながりを取り戻そうとするかのように、チリにいた頃の自分の話を、そして家族の話を「ぼく」にする。そんな彼女にとってのいまの最大の問題は家。父親の世話をしていた姉は思い出の詰まったその家を売ろうとしないが、クラウディアは新たな出発のために売却を主張。そうしたクラウディアの話を聞く「ぼく」とクラウディア、大人になった2人の関係が始まり、2人でマイプにいる「ぼく」の両親の家を訪ねたりする……。
最後の「みんな元気」では、ようやくエメが「ぼく」の原稿を読むことに同意する。「ぼく」はエメの意見が訊きたくてたまらないが、彼女はなかなか言わない。ところがあるとき、「突然、ふいに、エメは小説のことを話し始めた。気に入ったわ、でも読んでいるときずっと、なんとも言えないような感じ、動揺を抑えられなかった、あなたはあたしの話を語ってる、と彼女は言った。そしてそれをあなたに感謝しなくちゃいけないのかもしれないけど、そうじゃないと思う、あの話は誰にも語ってもらいたくないの」と言われて抗弁するものの、考え込んでしまう。そしてエメに去られ、「ぼく」は原稿を考え直す。
ぼくは小説に戻った。変更してみる。一人称から三人称へ、三人称から一人称へ、二人称にさえ。/語り手を遠ざけ、近づける。そして進まない。進んでいかない。舞台を替える。消す。たくさん消す。二十、三十ページ。その本のことを忘れてしまう。少しずつ酔いがまわり、眠ってしまう/そしてその後、目が覚めると、詩を書く。(略)
果たして「ぼく」は原稿(小説)を1つの作品としてまとめあげることができるのだろうか。いずれにせよ、『家への帰り方』には、こうした小説を書くという行為に対する叙述が随所に見られ、エメという存在自体、一人の登場人物でありながら、作家としての「ぼく」に対する批判の象徴、あるいは「ぼく」の成長を浮かび上がらせるものとして表されてもいる。
もう1つ、『家への帰り方』には前2作と大きな違いがある。それはピノチェト独裁時代への言及である。1973年9月11日、アメリカの支援を受けたクーデターでアジェンデ社会主義政権が倒れたあとに始まるピノチェト独裁体制は1990年まで続く。おびただしい人々が逮捕、拷問、誘拐され失踪者となり、100万単位の人々が他国へ亡命せざるを得なくなったと言われるが、そんな強権的な政治とは別に、新自由主義をモットーに国の経済を好転させた時期があった。そのため、チリ国内は親ピノチェト、反ピノチェト、そして政治に関わりをもとうとしない人の3つに分かれる。そんな国内のありよう、人々と政治との関わり方に対する証言が『家への帰り方』の匿名の(とはいえ多分に作者自身と思われる)語り手の口から随所でもれる。そのいくつかを見てみよう。
1985年の地震の頃、「ピノチェトは、ぼくにとっては、時間のことなどお構いなしに番組を動かすテレビのパーソナリティだった。そのせいで、いちばんいいところで番組全体を中断するつまらない国有放送のせいで彼を憎んでいた。ずっと後になって、ろくでなし、人殺しということで憎悪したが、そのころはそんな場違いなショーを見せるということだけで憎悪していた。だが、ぼくの父はなにも言わずにそれを見ていた。いつも口にへばりついているタバコを深く吸い込むこと以外身動きひとつせずに」
地震後、授業が再開されたとき、主人公は体育の教師に、「共産主義者であるのはとってもひどいことなんですか?」と訊くが、その教師は「君がそういうことを話すのはまずいよ、と彼はじっとぼくを見つめたあとで言った。こうしたことを話すのはまずい、そんな時期にわたしたちは生きてるってことしか君に言えない。でもいつかこうしたことを、どんなことでも話すことができるようになる」と言う。
両親やその友人たちがラジオのニュースを聞いて泣いたり、呆然としたり、家宅捜索や死者たちの話を何度も目撃したというエメの話を聞き、「そんな小説みたいな話は親たちの作り話だ、とそのときぼくは思ったし、いまもそう思う。そんなふうに、その作り話は親たちのものだと信じながらぼくたちは育った。彼らをけなしながら、そしてまた彼らの陰に安心して隠れもしながら。大人たちが人を殺したり、殺されたりしているとき、ぼくたちは隅っこで絵を描いていた。国がぼろぼろになっていくときに、ぼくたちは話すことを、歩くことを、船や飛行機の形にナプキンを折ることを学んでいた。その作り話がされるとき、ぼくたちは隠れん坊をしたり、失踪ごっこをしたりしていた」
こうして「ぼく」は独裁下にある80年代を思い出し、その思い出をつくっているエピソードをも綴っていくが、サンブラは独裁を断罪するときにありがちな、残虐なシーンを写実的に描くことはない。むしろ、独裁体制下で言論の自由を封じられた親と政治に無縁な子、そして民主主義が戻った後でも「ピノチェトは独裁者だった。人々を殺した。でも少なくとも、その時代には秩序があった」という人心が分裂したチリの現在を嘆く親とその親に批判の目を向ける子という両者の間の葛藤を言葉数の少ない、さらりとした文章で綴ることで、その2つの世代の間の溝をより鮮明に浮かび上がらせている。
サンブラは『家への帰り方』では、小説の書き方、あるいは小説のあり方、ピノチェト独裁時代、世代間の亀裂、誰もが抱く孤独といったものを、前2作以上に大きく扱って物語世界を拡大し、前2作で示したような新たな文学を創りだす書き手としての資質をいかんなく発揮しており、この作品がサンブラの評価をさらに高めたのもうなずける。
サンブラについては邦訳の解説に詳しいが、少し書いておきたい。サンブラは1975年、チリのサンティアゴで生まれた。詩人として文学活動を開始し、『無駄な入り江』(1998)、『引っ越し』(2003)といった詩集を出しているが、彼の名を広めたのはやはり散文作品である。『盆栽』はチリ批評家賞、チリ図書協会賞を受賞、『木々の私生活』は2010年のフランスのマレ賞の最終候補、イギリスの国際IMPACダブリン賞の候補となり、『家への帰り方』は2012年にチリのアルタソール賞とチリ図書協会賞、2013年に同書の翻訳がイギリスのPEN賞を受賞。また、フアン・ガブリエル・バスケスの『物の落ちる音』とともに、フランスのメディシス・外国小説賞の、そしてラス・アメリカス賞の最終候補の1冊となった。
冒頭で触れた初の短篇集『マイドキュメント』は、「ぼくの父はコンピュータで、母はタイプライターだった。/ぼくは何も書いてないノートだったが、いまは本だ」で終わる表題作を始め、癖のある同級生たちを描いた「国立高校」、メキシコでタクシー強盗に襲われるチリ人カップル「ありがとう」、なんとか禁煙しようとする男「ぼくはとてもうまくタバコを吸っていた」等々、味わいの違う11篇の作品から成り、それぞれ短篇のよさを楽しませてくれる。同書は2014年、チリのサンティアゴ州賞を受賞、ガルシア=マルケス短篇賞の最終候補にもなった。また、アメリカでは『ボストン・グローブ』新聞、NPRの2015年のベスト・ブックの1冊に挙げられたし、その他『ニューヨーカー』をはじめ多くの雑誌・新聞がその素晴らしさを喧伝している。
このように文学賞を受賞する、あるいはその候補となるということは作品が評価されていることだが、これまで出した4作が4作ともそんな評価を売る作家も珍しい。サンブラは2010年にはイギリスの雑誌『グランタ』で最も優れた若いスペイン語作家の1人として選出されたが、その期待に十分応えており、2013年には作品全体に対してオランダのクラウス賞が授与された。最新作は『ファクシミリ』(2015)という作品だが、本が手元になく、ネットを調べてもどんな作品なのか要領を得ないので、またの機会に。
*本文中、拙文最初の訳以外は、『盆栽』、『木々の私生活』からの引用は
『盆栽/木々の私生活』(松本健二訳、白水社)を使わせていただきました。
(2016.2.15)
|

